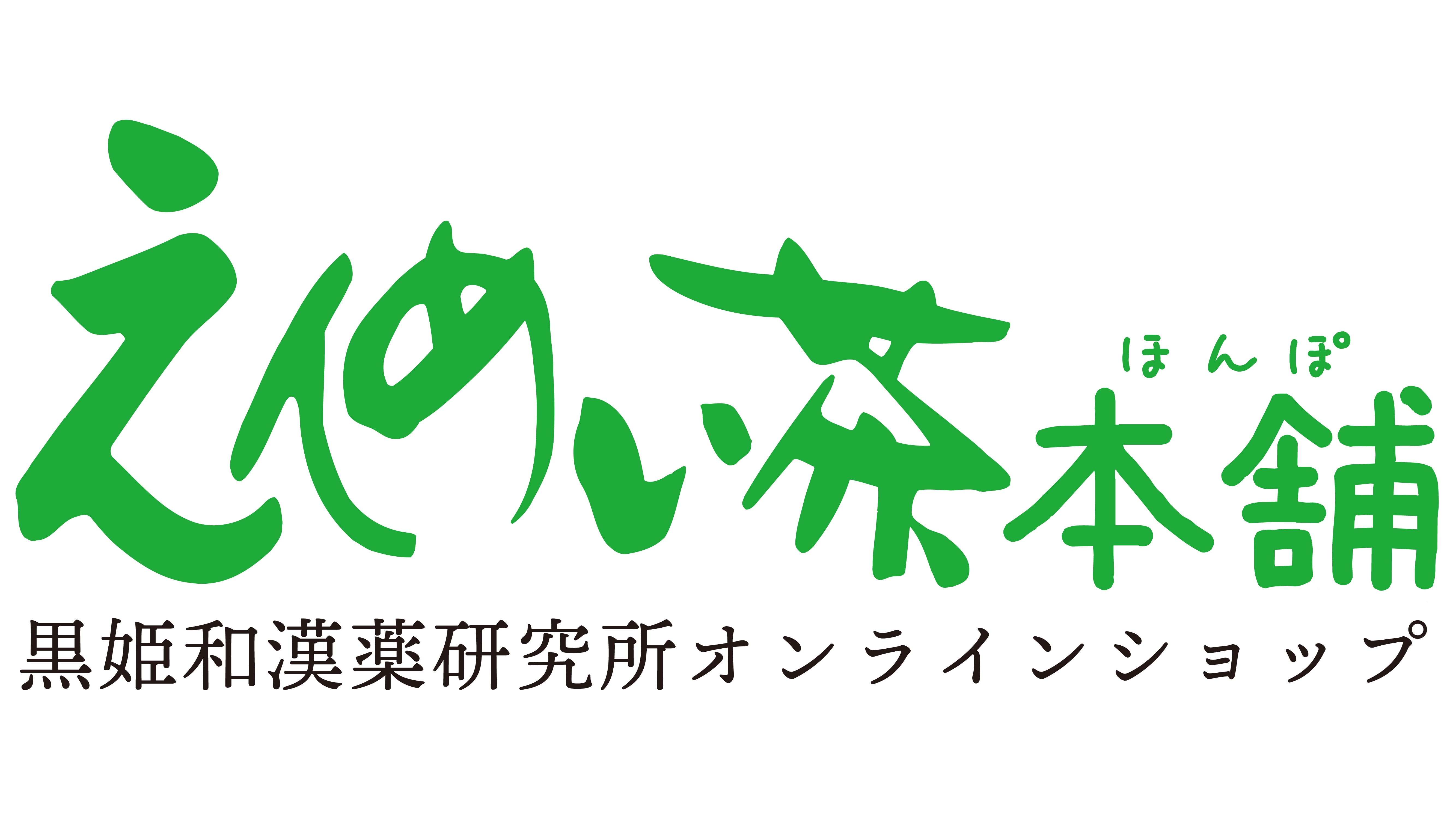〇「こどもの日」と「端午の節句」は別の行事
5月5日はこどもの日ですが、「端午の節句」を思い浮かべる人もいることでしょう。
実は「こどもの日」と「端午の節句」は同じ日ですが、別行事なのです。
「こどもの日」は国民の休日に制定されており、“こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する日”。男女関係なくすべてのこどもが対象となる日です。こどものお祝いはもちろんですが、“お母さんに感謝する日”でもあったのですね。
一方、「端午の節句」は中国から伝わった風習で、古くから男の子の健やかな成長を願って五月人形を飾り、外にはきれいな鯉のぼりを揚げてお祝いします。

〇どうして鯉のぼりを飾るの?
「鯉」という魚は、強くて流れが速くて強い川でも元気に泳ぎ、滝をものぼってしまう魚。そんなたくましい鯉のように、子どもたちが元気に大きくなることを願い、また難関を鯉のように突破し立身出世してほしいという願いも込められています。
真鯉の上を泳ぐ吹流しには、青、赤、黄、白、黒の五色が使われています。子どもの無事な成長を願い、悪いものを追い払う魔除けの意が込められています。
黒姫和漢薬研究所・えんめい茶本舗のある長野県では「端午の節句」、「ひな祭り」、「七夕」などの行事が1か月遅れで行われる地域があります。そんな長野県では鯉のぼりを6月5日頃まで見ることができます。
〇月遅れで行事が行われるワケとは?
明治時代初めに、暦の考え方が旧暦(月と太陽の動きを合わせて標準にする)から、新暦(太陽の動きを基準にする)に変わったことによります。この時に暦に約一か月のずれが生じました。(明治5年12月3日→明治6年1月1日)
「ひな祭り」は「桃の節句」とも呼ばれますが、新暦3月3日の長野は、桃の開花には程遠い寒さです。「七夕」もまた、新暦の7月7日に行うと梅雨の時期で雨と重なってしまいます。そこで季節感を大切にして、1か月行事を遅らせる「月遅れ」を取り入れるようになったと言われています。

〇「こどもの日」の風習
①食べ物
・柏餅
柏の葉でおもちを包んだものが柏餅。柏の葉は、『新しい芽が出るまで落ちない』ことから、“子孫繁栄”の縁起を担ぐとされています。主に関東で食べられるようです。
・ちまき
もち米などを笹の葉で包んで蒸したちまきは、中国から伝わった食文化です。笹には殺菌効果があり、“無病息災”を祈る意味が込められています。主に関西で食べられるようです。
②菖蒲湯に入るのはなぜ?
ずっと昔、「端午の節句」では菖蒲の葉は香りが大変強いため、その葉を入れたお湯につかると、病気や悪いものを追い払ってくれると言われてきました。
③兜を飾るのはなぜ?
兜は昔、体を守るために使われていました。そのため子どもの身を守り、元気に大きく育つようにという意味が込められ、飾るようになったとされています。

〇まとめ
由来や意味を知ると、お祝いの気持ちや特別感もぐっと増すもの。「こどもの日」をより豊かに楽しむことができるでしょう。