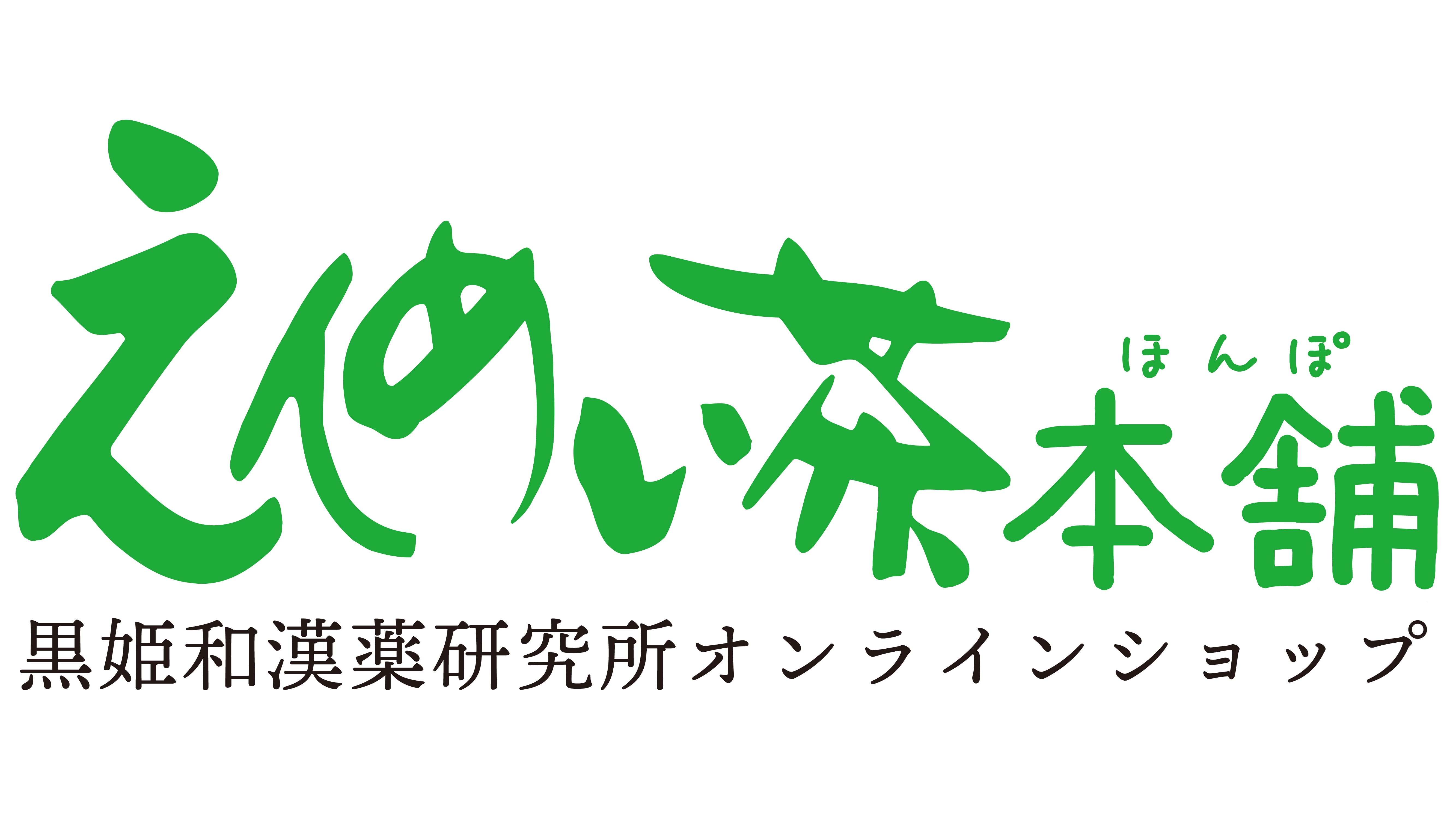NPO法人自然科学研究所 理事長 小谷宗司
信州大学農学部 元特任教授
(公社)東京生薬協会 元理事
日本全国で4月から6月にかけて、道端などで白い十字形の可愛い花を見たことはありますか? 繁殖力が非常に強く、独特の香りがあるため、庭や畑では厄介者として扱われることもありますが、食用や薬用として利用できる有用な植物です。今回はこのドクダミについて知っていきましょう。

Houttuynia cordata Thunb. (ドクダミ科 )
日本から中国,ヒマラヤ,東南アジアにかけての広い地域に分布し、やや湿り気のある林床や日陰地に生育している多年生草本植物です。ドクダミは梅雨の頃には白い4弁の花を付けます。実は、花弁に見える部分は植物学的には花穂を包む葉が変化した総包片であり、その中心から伸びた軸の上に黄色に密生するのが花です。
植物名の由来は、生の全草には特有の臭気があるので「毒溜め」から変化したとか、毒を矯(た)めて除く「毒矯め」。又は薬草としての効能を認めた「毒痛み」などが語尾を変化させドクダミとなったといわれています。
漢名は「蕺(じう)菜(さい)」と書きます。その説明によると「蕺菜は湿地、山谷の陰処に生じ、また能く蔓性する。葉は蕎麦に似て肥え、茎は赤紫色」とあります。
生薬名では「十薬」と書きますが、貝原益軒の大和本草の「蕺菜、ドクダミと云い又十薬とも云う、甚臭あしし、家園にうふれば繁茂して後は除きがたし……和流の馬医之を用い馬に飼ふ、十種の薬の能ありとて十薬と号す云う」によるものです。また、重薬と書くこともあり、これは当時の人達たちの生活に重要な薬だからと理由づけていますが、あて字ということになっています。また、十薬自体も蕺菜からの転用であろうとも云われています。

ドクダミの効能
ドクダミは日本薬局方にも収載されており、便通薬や整腸薬として、又高血圧・狭心症・動脈硬化などの予防の目的で広く民間薬や茶剤として用いられています。日本固有の民間薬のように思われていますが、東アジアにかけて広く分布しており、中国では魚腥草と称し、性味は辛・寒で清熱し解毒する、利尿し腫れを消すなどの効能があり、肺炎、肺膿瘍、熱痢、水腫、痔瘡などの要薬として位置付けています。
悪臭の成分は、デカノイル-アセトアルデヒドを主とする脂肪族アルデヒドであり、優れた抗菌作用を持つことが知られています。
日本ではこの独特の臭いがあるためにあまり好まれませんが,ベトナムではハーブだけでなく、野菜としても利用され、春巻きなどの具に加えられているそうです。日本人の感覚からすると、まさに驚きですね。

まとめ
アジア各国で広く利用されているコリアンダー(コエンドロ)も特有の香りを持ち、日本の食文化では初めは戸惑いがあったようですが、次第に馴染んできたようです。近い将来、日本でもドクダミがハーブや野菜に仲間入りする日がくるかも知れません。
薬を離れた用い方として、生葉をコップに差し冷蔵庫に置けば消臭効果抜群ともいわれますし、乾燥させて火を入れると独特の香りが消え、お茶として飲むのもいいかもしれません。
文献
牧野和漢薬草大図鑑(北隆社)、日本の野生植物(平凡社)、中薬大辞典(小学館)、日本薬局方(廣川書店)