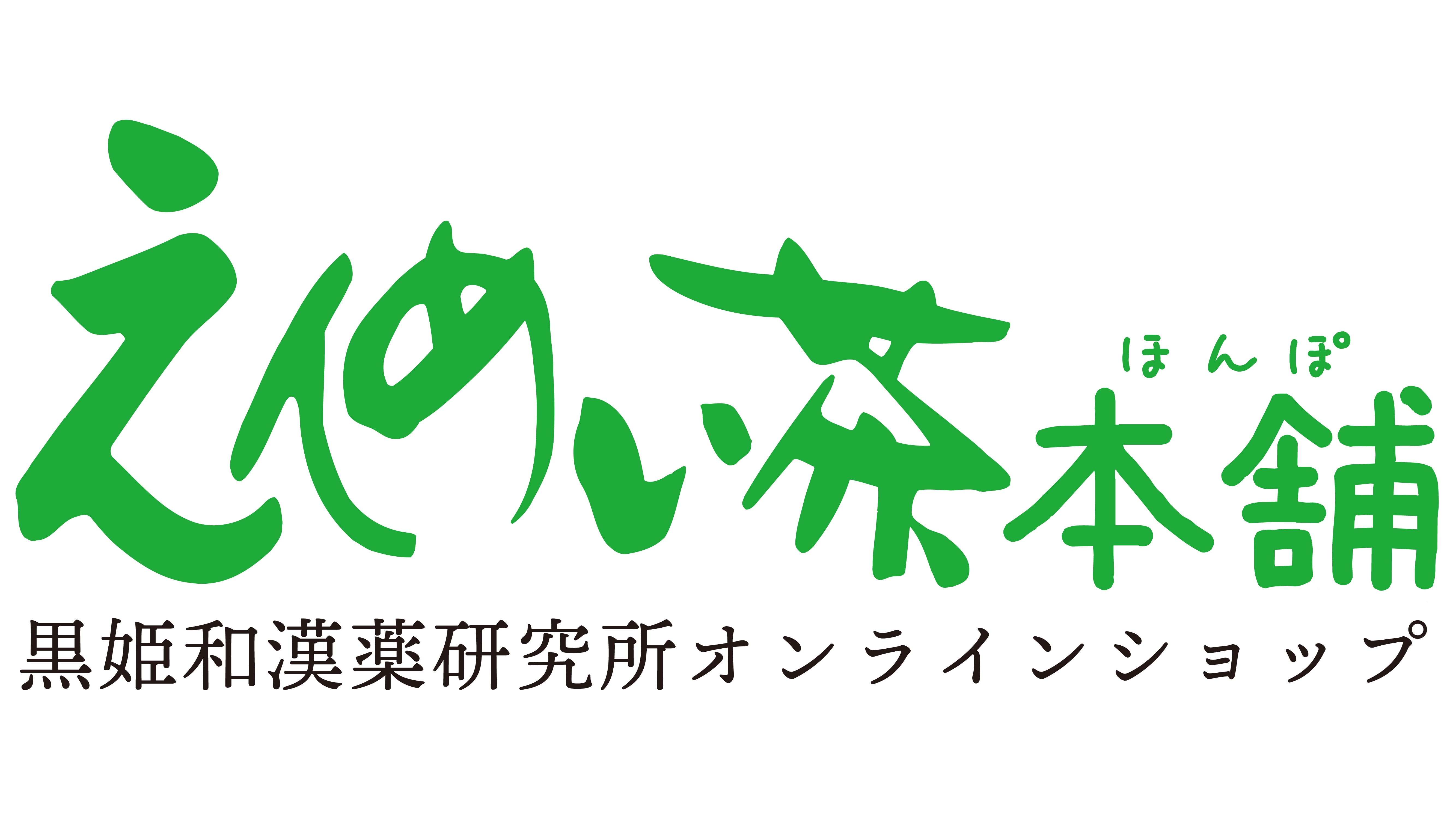近年、我が国において薬用植物の国内栽培についての機運が盛り上がってきました。薬用植物の栽培における、除草・殺虫・殺菌対策について述べていきましょう。
薬用植物の国内栽培について
医薬品(漢方薬ほか)の原料となる生薬の供給は、現行約9割が輸入に依存しています。
近年、中国産生薬の価格の上昇、品質のばらつき等の課題が顕著になりつつあります。
これを解消するには、国内における薬用植物生産量の増加が必須の要件となり、消費者の安全・安心の観点からも、トレーサビリティーが明確な国内産生薬の確保が注目されているところです。
農地の活用
農産物生産の経済的不安定さや、農業の後継者不足等により、全国規模で遊休放棄地の拡大を招いています。この農業の活用化策のひとつとしても、薬用植物の栽培が注目されており、その栽培について平成25年度(2013年)からは、国の補助金事業も開始され、全国の自治体等でも栽培の関心が高まっています。その延長で、生薬の全国消費量の約50%を国内生産を目指して、、全国各地で薬用植物の栽培が実施されています。
雑草対策・害虫対策・病気対策
薬用植物の栽培については、野菜や穀類などとは大きく異なり、医薬品の製造に該当し、医薬品医療機器等法(旧薬事法)という法規制をクリアしていく必要があります。
そのために、栽培の実施時にはかなりの制限が設けられています。それは雑草対策と、害虫対策、病気対策の問題です。
個人的な見解ですが、現在の農業生産の現場において、農薬の使用は不可欠です。あまり手をかけず、より短期間に、より多くの農産物を得る目的で品種改良が進み、現在の農産物は本来の性質から大きく異なる生育特性となりました。自力では十分生育できないと表現してもよいと思います。
そこに除草剤・殺虫剤・殺菌剤の必要性が出てきます。使用にあたっては、野菜・果樹等の個別の指定農薬制度があり、無制限の使用は禁じられています。農薬は体に有害となる側面も有しているからです。
杜仲(トチュウ)は虫が付かない?
黒姫和漢薬研究所が、長野県内4か所で管理する自社農場の一つ「塩尻地区」の杜仲についてです。「杜仲は虫が付かない」と言われていたのは過去の話で、本年度は「トチュウウスクモヨトウ」による害虫被害にあいました。薬用部位である葉がすべて食べられ、残るは茎のみとなってしまったのです。広大な畑がほぼ全滅です。
中国の湖南省で発見された本種は、杜仲の葉のみを食べる単食性とされ、日本には存在しない害虫でした。地球温暖化による活動域の拡大なども原因のひとつです。
防除対策としては、現行「本種に対する登録農薬はないため、以下のような耕種的手法による防除対策を実施します。
①幼虫の発生初期に、食害葉を見つけ、幼虫を駆除する。
②防虫網を木全体にかけ、成虫の飛来・産卵を防ぐ。となっています。
まとめ
杜仲のみならず薬用植物を原料とした製品を、消費者の皆様にご理解いただきたいことは、これらはとてつもなく手間ひまかけて生産した製品であることです。さらには、ヒトの健康維持にとって大切な要素は、化学合成された医薬品的な物質ではなく、人類の疾患に対する経験則の中から生まれた、天然の植物(薬用植物)の位置づけが大きく変わってきたということです。
有効・安心・安全な生薬の需要が増加し、国がそのための対応に力を注ぎ、多くの企業や公的団体などが、この栽培事業に対して知っていただければと願っています。
NPO法人自然科学研究所
理事長 小谷宗司
国立大学法人信州大学農学部 元特任教授
公益社団法人東京生薬協会 元理事