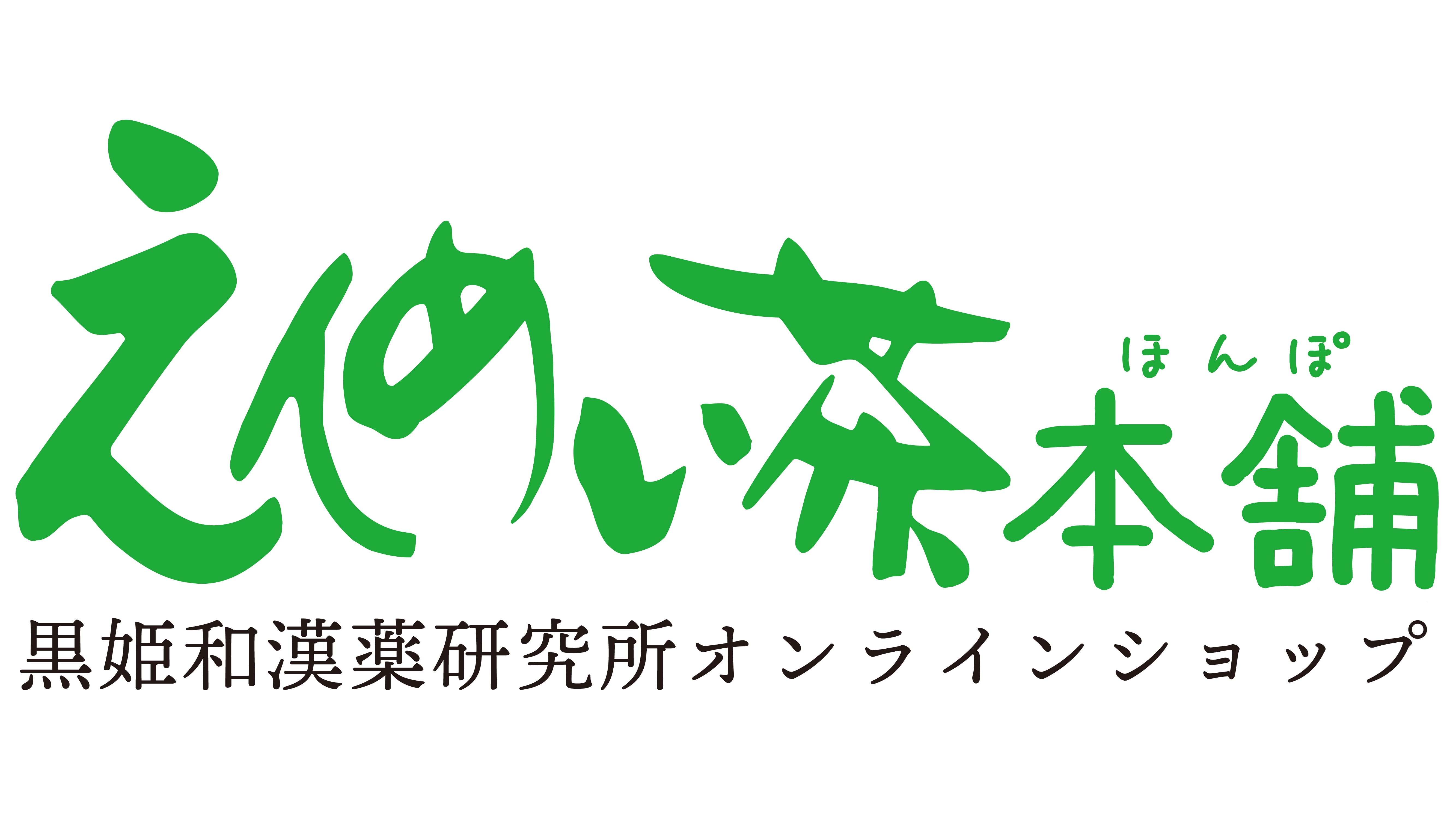『マユミ』は秋が最も美しい
オレンジ色かわいらしい実際をつけるマユミは「ニシキギ」の仲間で、秋に紅葉と実の見頃を迎えます。「ニシキギ」とは漢字で書くと「錦木」のことで、マユミもその名にふさわしく、とてもきれいに紅葉します。古来より「弓」の材料として使われてきたため「真弓」という名前が付けられたとも言われています。
マユミの開花時期は5~6月頃ですが、花よりも実のほうが注目されることが多いようです。 マユミは実は鮮やかなオレンジ色で、小さなサイコロのような四角形をしています。実が熟すと表面が破れて、中から種が飛び出してきます。
マユミには実をつける雌木と、実をつけない雄木があるとされています。 そのため、実の鑑賞を目的に栽培する場合は、雌木を育てるとか。 庭に野鳥がやってきて、にぎやかな光景が見られるのもまた楽しみです。

『山ブドウ(ヤマブドウ)』は紅葉の始まり
周りの木々よりも早く色づき始め、特に山間部では秋の訪れを知らせる始まりの合図。 ツタよりも早く色づき始める大葉のマントは黄色、オレンジ、赤、赤紫など鮮やかに色づき、山地の道路沿いや林縁を大きな葉で覆うので見つけやすいです。
ヤマブドウは、雌雄異株のため雌株にしか結実しません。 また山に自生しているヤマブドウの雌株の比率は30%前後と、雄株が圧倒的に多く、天然ヤマブドウの果実はなかなかお目にかかれないのが現状です。実が熟してぶら下がったまま紅葉している様子は貴重な光景です。

『イチョウ』の葉が真っ先に落ちる理なぞ
イチョウの落葉が一斉と言っていい程、短時間に落葉することはよく知られています。早いと2時間位で樹が裸になることもありますが、普通は1日でほぼ全葉が落ちてしまいます。「イチョウの葉」が一斉に落ちる理由は、葉柄の基部に「離層」という組織が形成され、幹から葉への水分や養分の流通が遮断されることで起こると言われています。この過程により、葉が枯死し、最終的には葉が脱落します。イチョウでは、全ての葉に離層がほぼ同時に形成されるため、一斉に落葉することが見られます。イチョウに見られる特別な仕組みは、一般的に11~12月にかけてです。
●黄葉日(おうよう)とは
イチョウの黄葉の日とは葉が黄色に変わった状態になった最初の日です。 簡単に言うと、イチョウが綺麗な黄色となり、これから黄葉シーズンとなる合図の日です。
●落葉日(らくようび)とは
イチョウの落葉日とは、気象庁が観測する標本木のイチョウの葉が80%以上、落ちた日(落葉した日)です。わかりやすく述べると、黄葉シーズンの終わりを告げる合図の日です。
 『クマザサ』の名前の由来
『クマザサ』の名前の由来
大型のササ類クマザサ。 新葉のうちは全面が緑色ですが、秋が深まって寒気にさらされると、さらに葉の縁が白く枯死して模様のようになります。この様子を歌舞伎のメイクである「隈取(くまとり)」にちなんで、日本の植物学者の父である「牧野富太郎」氏がクマザサと命名したと言われています。隈は、日向より日陰に植えたほうが美しく育つようです。
冬の寒さにも負けないクマザサは、冬眠前の熊や冬眠明けの熊のデトックス作用に優れ、栄養源ともなります。