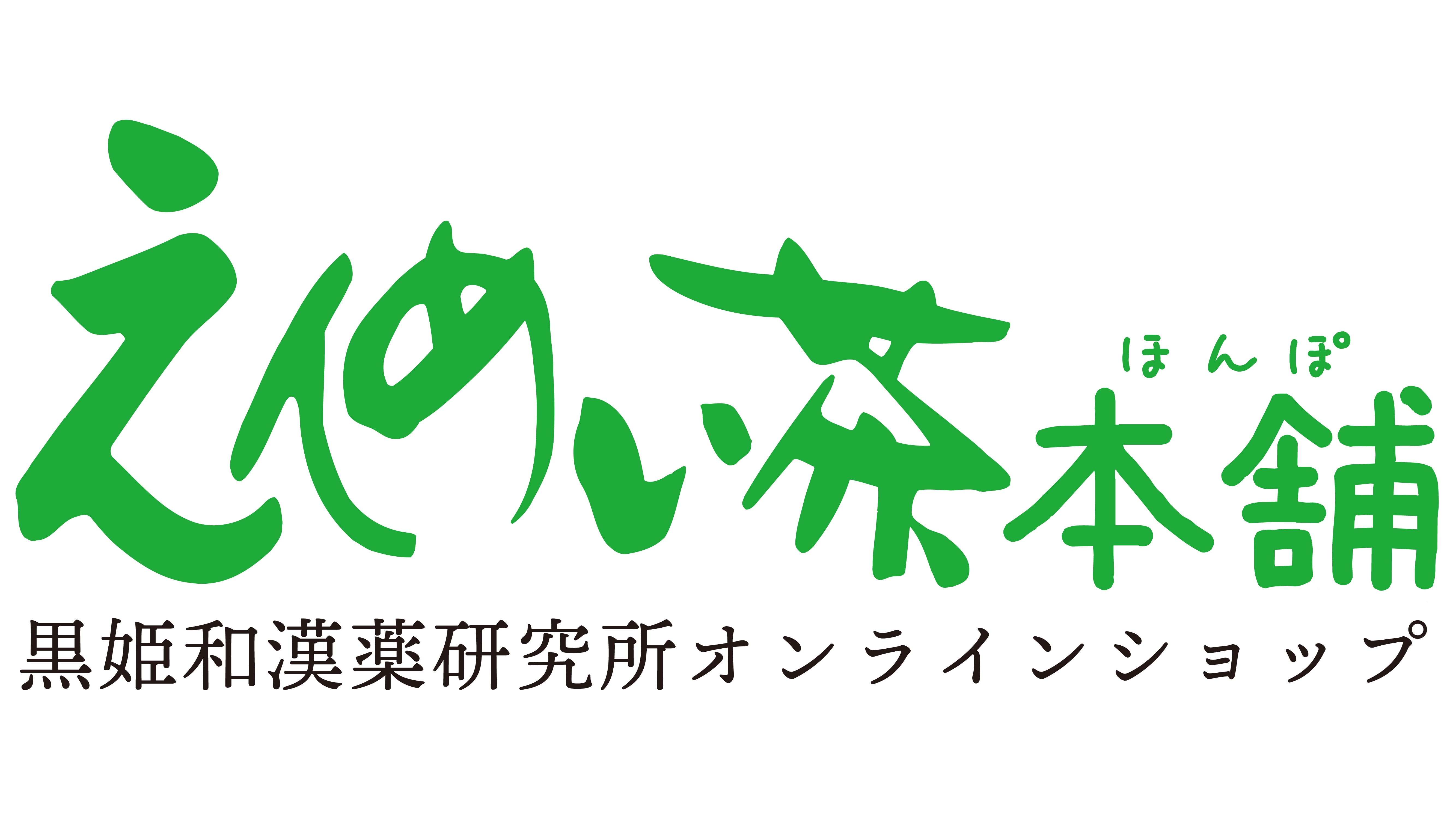NPO法人自然科学研究所 理事長 小谷宗司
国立大学法人 信州大学農学部 元特任教授
公益社団法人 東京生薬協会 元理事
近年大きくクローズアップされているものにアレルギー疾患があります。花粉症や食物アレルギーなどが代表的なものとして挙げられますが、実は、医薬品、金属、ダニ、鶏卵など様々なものもアレルギー原因物質になり得るのです。このようなアレルゲン(抗原)と呼ばれる一般的には無害な物質に対して、過剰な反応を生じさせる免疫系の機能不全の1種がアレルギー疾患です。

体を守る免疫
人が健康に生きるために、免疫機能はとても重要な働きをしています。免疫と言っても、五感で感じられないため気が付かない存在ではありますが、私たちの生活はいろいろな食べ物や人混みの中などで、数え切れないほどの微細な異物、細菌などと遭遇しています。
免疫とは、私たちの体に入ってくる、これら細菌などの有害物質と闘い、体を守るシステムのことです。私たちの体は優れたこの仕組みによって、気づかないうちにいつも守られているのです。
免疫には種類がある?!
免疫システム(抗原抗体反応)は、生まれながらに持っている抵抗力「自然免疫」と、生きていくうちに後天的に力をつける「獲得免疫」の大きく2系統があります。
「自然免疫」は、相手を選ばず、細菌の侵入や体内のがん細胞に対して同じように働き、同じ有害物質に繰り返し侵入されてもその効果に変化はありません。風邪にかかりやすい人、かかりにくい人は、この「自然免疫」の働きが大きく影響しています。
一方で「獲得免疫」は、「自然免疫」をくぐりぬけて侵入してきた有害物質に対して集中攻撃を行います。おたふくかぜや麻疹などのウイルスに感染した場合に闘い、一度目の敵を記憶し、同じ敵を素早く鎮圧するので同じ病気にはかかりません。これは『免疫記憶』という仕組みのおかげです。「獲得免疫」を活用した予防が、予防接種になるわけですね。
このように体にとっては有益な免疫システムですが、ときに必要以上に作用したり、あるいは不適切に作用したりすることがあります。これがいわゆる『アレルギー反応』です。反応の機序は判っていますが、その原因は十分に判っていないのが現状です。
このアレルギー反応にはⅠ型、Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型と4つの型があり、このうち、アトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎、食物アレルギー、花粉症、気管支ぜんそくなど一般的なアレルギー疾患は、主にⅠ型とⅣ型に関わっています。Ⅰ型は即時型アレルギー、Ⅳ型は遅延型アレルギーと呼ばれています。
アレルギーは治る?!
『免疫記憶』の仕組みは、「ひとたび身体が記憶してしまうと二度と忘れることはない」というのが特徴です。したがって、身体の記憶が消えないという意味では、「アレルギーは治らない」といえます。ただ、幼児期から発症するアレルギーマーチと呼ばれるものは、経年とともにある症状が改善するという経過もあります。
アレルギー反応によって起こる諸症状は、決定的な治療薬はまだありませんが、抗ヒスタミン剤や抗アレルギー用薬などで症状を抑えたり、コントロールすることができます。接触や皮膚の乾燥、感染によって起こる症状も、予防や対処の方法があります。その意味では、「アレルギーは治る」という表現も決して間違ってはいないでしょう。

まとめ
しかしながら、アレルギー性疾患は「慢性疾患」の側面が強く、ねばり強く治療に取り組み、日常生活に対しても工夫が必要になってきます。そのため治療に際しては、治療薬を長期間連用する可能性が高くなり、それだけ薬による副作用の問題が関わってきますので注意が必要です。まずはアレルギーを発症しないためにも、普段から自分の体をよく観察し、よく知ることで予防・対策を行っていくことが大切になってきます。