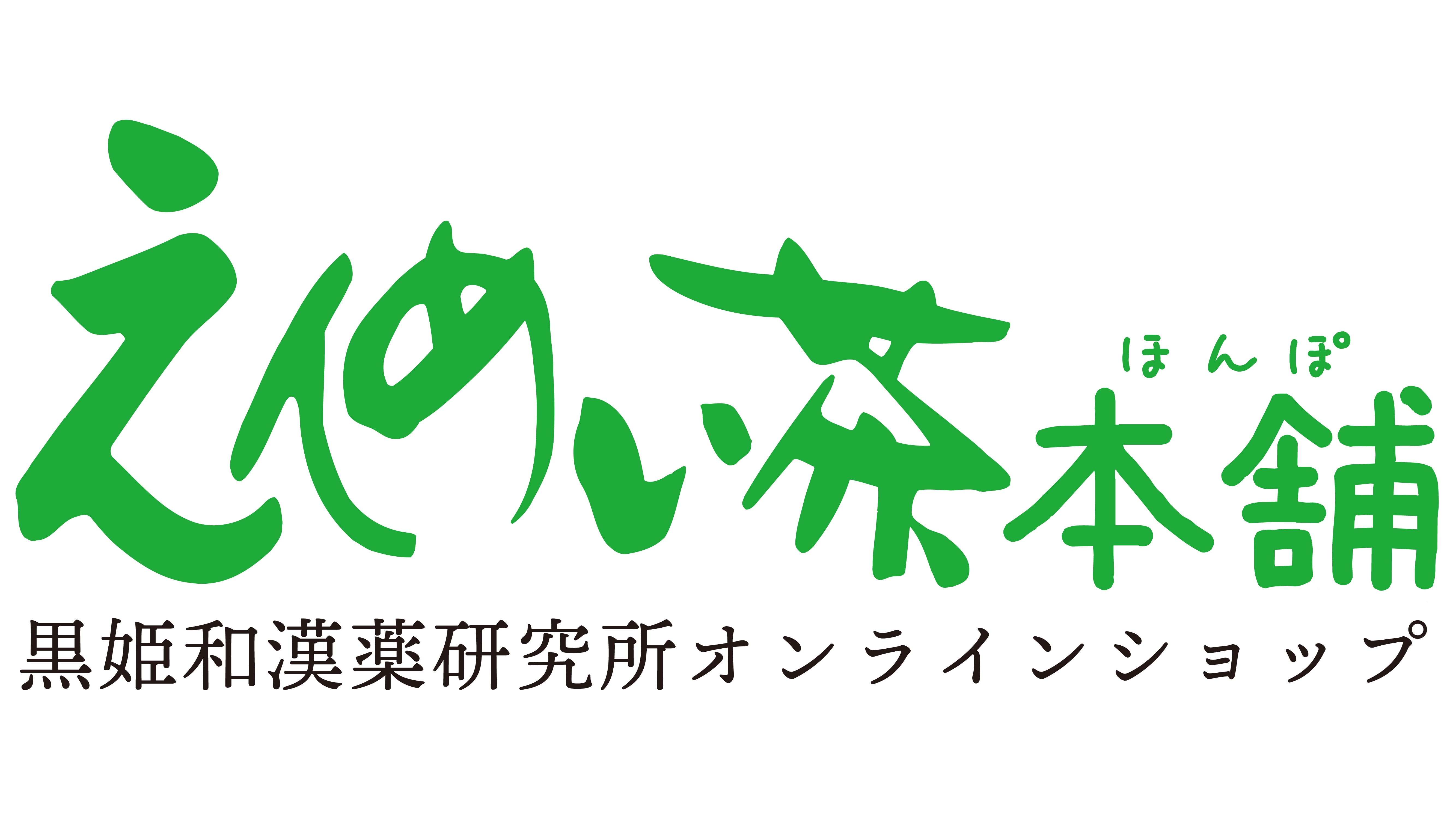冷えは寒い季節だけ起こる症状ではありません。 夏になると、外は蒸し暑く、日差しは照りつけるように強いのに、手足はいつも冷たいなど、夏の冷えに悩む人が増えています。冷え性ではないと感じている人、夏の暑さで体の冷えに気付かないという人も要注意!
冷えは病気ではありませんが、血流が悪くなりカラダが冷えることで、胃腸の不調・不眠・肩こり・頭痛などの不快な症状が現れるほか、免疫力の低下により病気にかかりやすくなる厄介者です。たかが冷え性と思わずに原因と対策を知って改善していきましょう。

□夏に冷えが起こりやすい原因はさまざま
① 室内と外気の寒暖差
冷えとは、手足やお腹、腰など、体が「冷たい」、「寒い」と感じることをいいます。冷房の効いた室内に長時間いると体は体温を維持しようとし、血管は収縮します。そのため血液の巡りが悪くなり、体の末端である手足から冷えていきます。また外の暑さと冷房の効いた室内との温度差が大きいと、体はうまく対応できず、自律神経が乱れ、同様に血液の巡りが悪くなり、体の手足から冷えていきます。特に寒暖差が大きい場合は、冷えだけではなく肩こりや頭痛、倦怠感などの不調を引き起こす「寒暖差疲労」が起きやすくなります。
② 食生活の乱れ
飲食物の消化に適した胃や腸の温度は、37℃前後です。 夏は冷たい食事に飲み物、おやつにアイスクリーム、夜はビールと、一日を通して冷たい物を食べる機会が増えます。 暑いから少しアイスクリームや冷たい飲み物などをとり過ぎると、胃腸が冷えて消化機能が下がり、内臓が冷えると、元の温度に戻すためにエネルギーを使います。 そうすると、本来のエネルギーが使われずに血液循環が滞り、冷えを招く原因になります。内臓が冷えるとお腹を下しやすくなり、暑い夏にお腹の調子が悪くなる人が多いのはそのためです。

□冷えから起こる症状
先に説明した通り、身体の冷えが血管を狭め、体中に栄養や酸素が行き渡りづらくなることから、以下のような症状が出やすくなります。
これが出たら要注意!
・頭痛・肩こり
・めまい
・食欲不振・体力減退
・疲労・倦怠感
・血行不良・むくみ
・便秘・下痢 など
また、筋肉量が少ない女性のほうが、冷えやすいといわれています。冷え性になって基礎体温が下がると、生理不順や生理痛の悪化などにつながることもあるため注意しましょう。

□夏の冷え対策
1. 食事内容に気を付ける
夏の冷え対策には、食事内容が重要です。 体温よりも温かい食べ物や体温を上げる食材の摂取を意識して、体温の低下を防ぎましょう。
・体温調節に役立つ食材を取り入れる
トマトやキュウリなど、夏が旬の野菜は身体を冷やしますが、冬が旬の野菜は、身体を温める効果があります。具体的には、根菜と並ぶ人やレンコン、ゴボウなどです。また、生姜や唐子などの辛味成分は、交感神経を刺激し代謝エネルギーを高める効果があるので、体温の上昇に役立ちます。
・発酵食品を取り入れる
納豆やキムチ、ヨーグルトなどの発酵食品は血流を促すため、積極的に取り入れましょう。
2. 日常生活の習慣を見直す
夏の冷え性は1日で発症するものではありません。日常的な習慣が積み重なり、症状が現れることがほとんどです。 まずは、冷えを起こさないように身体を温める服装を意識したり、冷房温度の調節をしてみましょう。
・気温差に注意する
室内の温度を高めに設定し、寒暖差を少なくするのも、夏の冷え性対策に効果的です。 外気との差が5度以上になると、肩こりや疲労感などの冷えの症状が出てくるともいわれているため、天候や状況に合わせて熱中症対策をしながら5度以内の気温差に収まるようにしましょう。
・規則正しい生活を心がける
朝早く起きて朝食を食べ、交感神経を活発化させる行動も、冷えの防止に有効です。朝から行動することで、夜にはリラックス作用のある副交感神経が優位に働き、やがて自律神経が整います。
3. 自律神経を整える
・入浴時は湯船につかる
夏に湯船につかるのは暑い…という方もいるかも知れませんが、夏の冷え性改善には効果抜群と言われています。 体温が上昇し血流改善にも効果があるからです。
38度~40度のぬるま湯に、20分程度入浴すると、身体の芯から温めることができます。湯冷めしないよう、入浴後はなるべく早く衣類を着用しましょう。
・太陽の光を浴びる
寒暖差疲労により自律神経が乱れると、不眠になったり眠りが浅くなったりする方がいます。睡眠の質を高めるには、幸せホルモンと呼ばれるセロトニン分泌が必要です。日中、太陽の光が浴びると脳内のセロトニン神経が活発になり、セロトニンの分泌を促します。セロトニンの分泌量が増えると、催眠作用のあるメラトニンの分泌量が増え、結果的に質の高い睡眠が得られやすくなります。20~30分程度動く簡単なエクササイズ(ウォーキングやピラティス・ヨガなど)もおすすめです。
・定期的に身体を動かす
ストレス解消や、冷え性のために血液循環の改善には運動やエクササイズが有効です。 特にふくらはぎは、心臓から一番目の遠い位置にあり、下から上へ血液ポンプの様な役割をしており、「第2の心臓」とも呼ばれています。ふくらはぎを揉んでマッサージをしたり、ストレッチなどをして、適度な運動で刺激を与えるのも効果的です。

まとめ
夏の冷えは、多くの人が経験する悩みです。 しかし、日常生活にちょっとした工夫を取り入れることで、冷えを改善することができます。 入浴や食事、運動などの普段の生活の中で自律神経を整えながら、夏を健康に過ごしましょう。
自分でできる対策を実践して冷え対策行い、快適な夏を楽しみましょう!