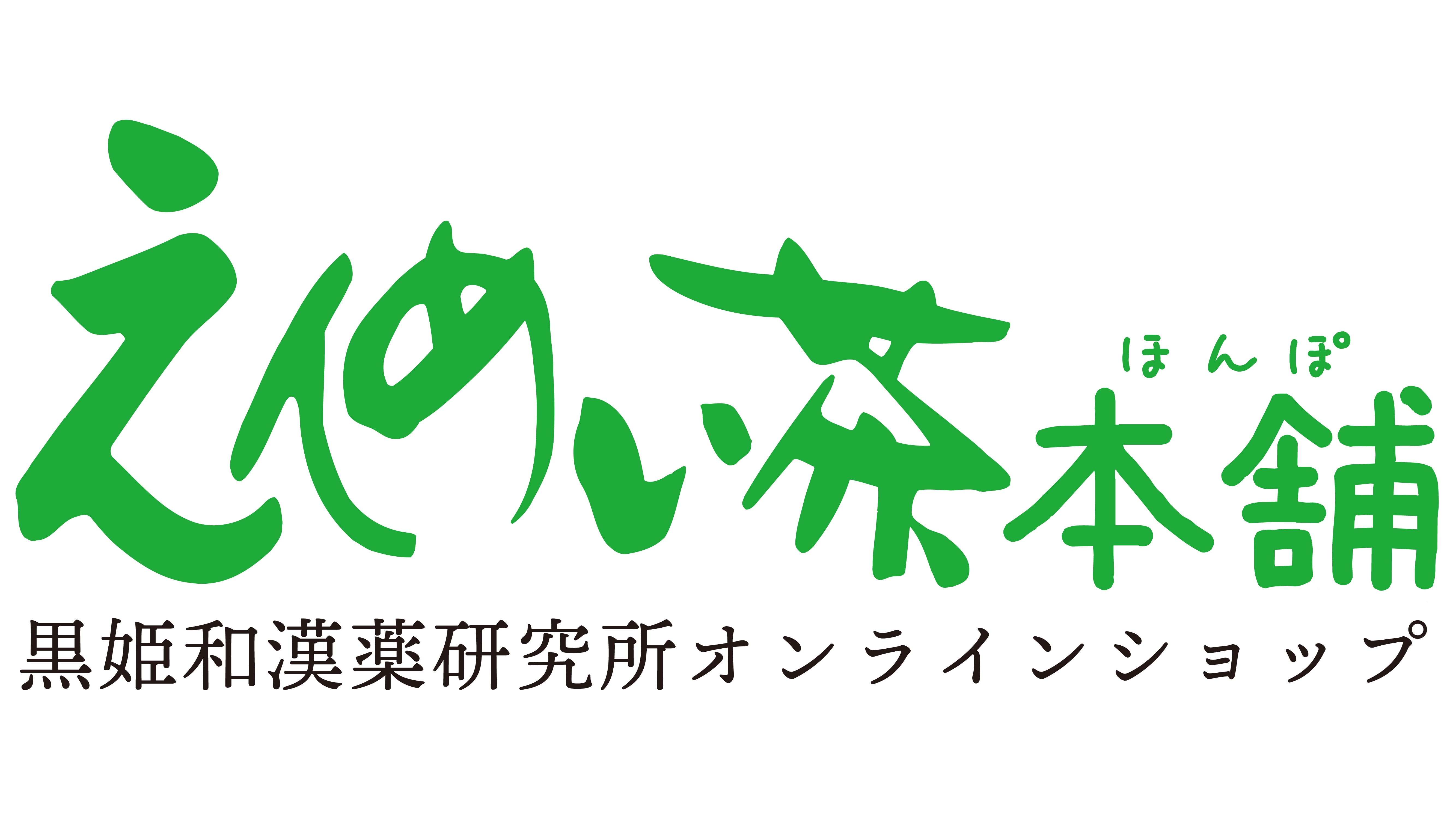NPO法人自然科学研究所 理事長 小谷宗司
国立大学法人 信州大学農学部 元特任教授
公益社団法人 東京生薬協会 元理事
天候の変化から起きる体調の変化をご存知でしょうか?
ここでは、天気が悪くなると、頭痛やめまいなどが起きる気象病について知っていきましょう。

地球温暖化と異常気象
地球温暖化は「地球全体の平均気温の上昇を指し、生態系に悪影響を及ぼす恐れがあると考えられる現象」と定義されています。その要因として、人間の産業活動に伴って排出された温室効果ガスが起因との説が主流とされています。この地球温暖化が要因で、世界各地では近年にない現象として異常気象が観測されています。

気象病や天気痛
天気や気温の急激な変化によって、自律神経が乱れることが原因で起こる疾患で、頭痛やめまい、むくみ、気分が落ち込む、古傷が痛むなどの症状が出るのが特徴です。体温調節や呼吸などの生命に欠かせない機能をつかさどる自律神経は、どんな時も体の働きを一定に保とうと機能します。しかし天気や気温の変化が著しいと、自律神経が無理をして、体の機能を上手にコントロールできなくなってしまいます。 今までは「気のせいかな?」と流していた人もいたかもしれませんが、実は天候と体調には、深い関係性があったのです。

気象病のメカニズムは?
気象条件が生み出す差が、どのようにして頭痛やめまいなどの気象病につながっていくのでしょうか? 気象病の直接の要因として、気圧や温度の差が急激に開くことで発症します。例えば、雨が降る前に気圧が急激に下がったり、温かい室内から寒い屋外に出たりすると、周囲の温度が激変し発症に至ります。耳の奥にある「内耳」がその変化を察知し、脳から自律神経を経て、身体に蓄積していた不調や疲労が症状として顕著に現れる。それが気象病のメカニズムとされています。
まとめ
始めにお話したように、特に近年に至って地球温暖化に伴う異常気象が多発しています。このことは体調不良を引き起こす要因が増加していることと同じです。普段から天気予報を確認し、天候の変化から起こる体調の悪化を予防しながら体調管理を行っていきましょう。(健康人生Vol.34)