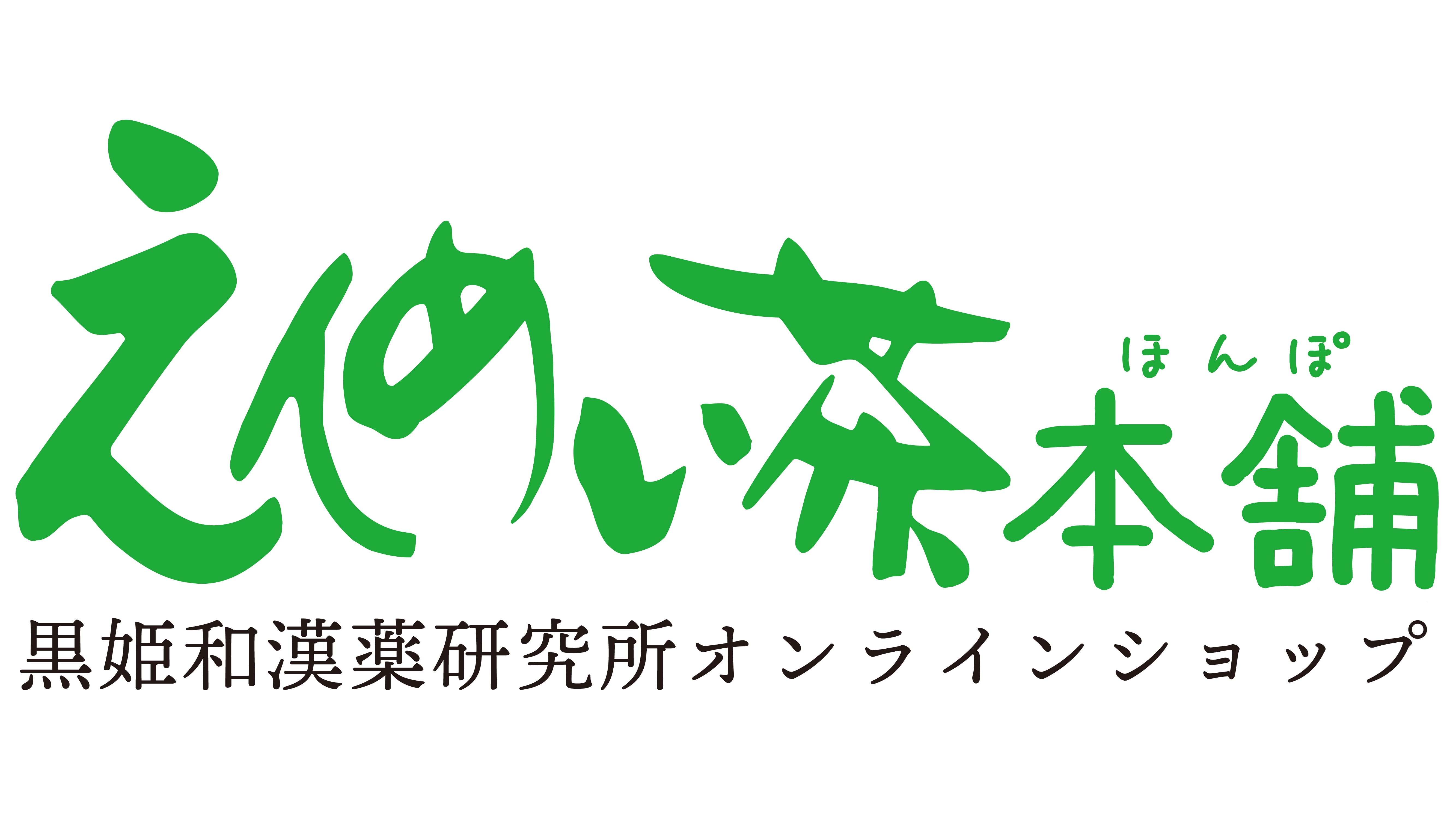「雷の多い年はお米が豊作になる」って聞いたことはありませんか? 今年は雨が降らず日照が続いたり、降れば豪雨、そして恐ろしいほどたくさんの雷が発生しました。
雷は「稲妻」とも読みます。 俳句の世界では、夏の季語は「雷」、秋の季語は「稲妻」になります。 なぜ、稲の妻と書くのでしょうか? 今回は稲妻の名前の由来について書いていきます。

稲妻の由来
古くから秋の雷は、稲を実らせると信じられてきました。
農業において、作物の成長に重要な役割を果たす養分のひとつに「窒素」があります。窒素は空気の成分の約8割を占めますが、植物は空気中の窒素を直接取り込むことはできません。
雷は放電によって空気中の窒素を窒素化合物に変え、これが雨に溶け込み土壌にもたらされ、それが天然の肥料になっていたと考えられています。 雷は稲を成長させる大切な存在であるため、「稲の夫(つま)」=現代では「稲妻」と呼ばれるようになったという説があります。
※日本の古語では「つま」は男女問わず配偶者の意味。

雷(プラズマ)の農業活用
先のお話で、雷の放電が植物に窒素をもたらすと言う説は、実際に実験も行われて実証されているそうです。雷を農業に活用する研究は、世界的にも進められていて、CO²排出削減にもつながる画期的な技術の可能性があると言われています。
農業用の肥料を作るときに、二酸化炭素が排出される温暖化が進み、それによって減った収穫量を補うために肥料が増産され、さらに二酸化炭素が排出されてしまう、という悪循環が生まれるのだそうです。
それに加えて、窒素循環の破綻という問題があります。 窒素循環とは、⾃然界で窒素ガスが微生物や動植物の働きによりアンモニアや硝酸に変化して、微生物などの働きによりまた窒素ガスに戻ることを⾔います。ところが現在、人間が作ったアンモニアや硝酸の量が、微生物等が窒素ガスに戻す能力を超えているため、余ったアンモニアや硝酸が土壌や地下⽔を汚染し、これに伴う温化ガスの発生が問題となっています。 この人間が作ったアンモニアや硝酸の約50%が窒素肥料なのです。
雷(プラズマ)の農業活用が、その窒素肥料問題を解決する新たな農業技術として、世界的に注目を集めているようです。

雷と季語
天気予報やカレンダーなどがない時代、季節のうつろいや天候の変化を読み取ることが、暮らしにとってとても大切だったためか、雷ひとつでも季節ごとに繊細に見分けてそれぞれに名前をつけています。
春
「春雷(しゅんらい)」
その春に初めて鳴る雷は「初雷(はつらい)」
桜の後に必ず降る花散らしの雨に伴うことも多く、啓蟄の頃の雷は「虫出しの雷(むしだしのらい)」と言ったりします。
夏
「雷(かみなり)」
上昇気流により発達した積乱雲によって起こる放電現象。
「雷雨(らいう)」「雷鳴(らいめい)」「いかづち」「遠雷(えんらい)」なども夏の季語です。
梅雨明けが近く鳴る雷は「梅雨雷(つゆかみなり)」と呼ばれます。
遠雷は、遠くのほうで聞こえる雷です。
秋
「秋雷(しゅうらい)」
「稲妻(いなづま)」「稲光(いなびかり)」大気中の放電現象の電光、光のこと。古くから稲を実らせると信じられていました。
冬
「寒雷(かんらい)」 寒の内に鳴る雷。
「雪おこし」「雪雷(ゆきがみなり)」「雪の雷(ゆきのらい)」雪国で雪の降り出す前に鳴る雷のこと。
「鰤起こし(ぶりおこし)」 初冬に北陸地方では鰤の漁が始まり、この頃に鳴る雷のこと。鰤漁の始まり、豊漁の知らせとされていました。
まとめ
いかがだったでしょうか、昔の人々の視点で雷のさまざまな顔が見えてきましたね。 そこに現代の化学が加わって、また新しい雷との関わり方が出来る日も近いかもしれません。ちょっと怖い存在の雷ですが、以前より雷を身近に感じられるようになると良いですね。